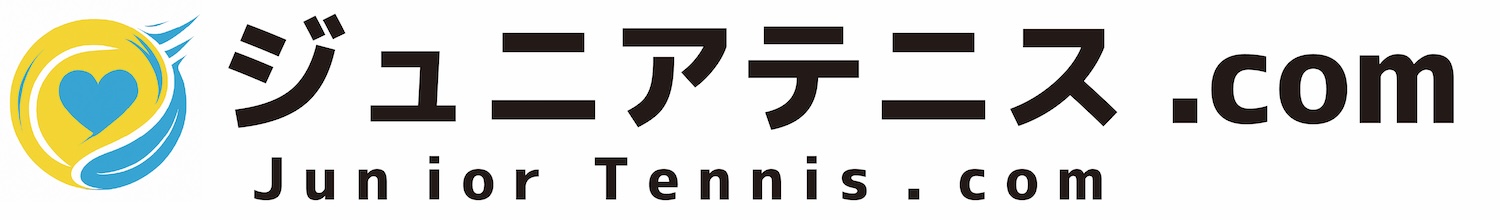食事のタイミングは、戦略の一部です。
このシリーズでは、ITF・WTA・ATPの3団体が合同で発表した「テニス選手向けの実践栄養ガイドライン」 をもとに、ジュニア選手の栄養をわかりやすく紹介しています。
第2回のテーマは、
試合前・試合中・試合後に“何をどう食べるか”。
テニスは、試合時間も相手も展開も読めないスポーツ。だからこそ、食事を「ただ食べる」ではなく、コンディションを整える戦略 として考えることが大切です。
今日は、勝ち負けに直結する3つのタイミングを物語として追っていきます。
試合の3時間前「準備の食事」は、静かな助走
試合当日の朝、選手が緊張を抱えながらも静かに準備するように、身体も“助走の食事”を必要とします。
ガイドラインでは、試合の3時間前に炭水化物を中心とした食事 をすすめています。
これは、テニスが長時間にわたりエネルギーを消費するスポーツだからです。
パン、パスタ、おにぎり、シリアル。
どれもお腹にやさしく、ゆっくりと力に変わっていきます。
逆に、脂っこいものや食物繊維が多いものは消化に時間がかかり、試合中にお腹が重くなる原因に。
● 試合前3時間の“整う食事”の例
たまごサンド+果物+ヨーグルト
おにぎり+焼き鮭+具だくさんの味噌汁
パスタ+シンプルなトマトソース+オレンジジュース
静かに整えていくような食事が、試合のスタートラインに立つ力になります。
試合直前は「軽さ」と「持久力」を両方もつ食べ物を
試合の30〜60分前。
ここは「満腹にしない」「でも力は切らさない」という微妙なバランスが必要な時間です。
ジュニアにとって最適なのは、小さくて消化がよく、すぐエネルギーになるもの。
バナナ、ゼリー、シリアルバー、薄いパンなど。
ほんのひと口の補給が、最初のゲームの集中度を高めてくれます。
試合まで緊張で食べづらい子もいますが、
“ひと口でいいから何か入れる”
この小さな習慣が、後半の粘り強さを確かなものにします。
試合中の補食は「粘り」を生む。エネルギーは枯れる前に入れる
テニスは、競技の中でも珍しく試合中に食べてもよいスポーツです。それは裏を返せば、試合中にエネルギーが枯渇しやすいということ。
ガイドラインでは、1時間あたり30〜60gの炭水化物の摂取が推奨されています。これは大人向けの数値ですが、ジュニアも“こまめな補給”が大切なのは同じです。
バナナ半分、ゼリー1つ、スポーツドリンクの小さめボトル。
小さな補給を重ねることで、「動けなくなる前に、動ける状態を保つ」という理想の流れが作れます。
エネルギー切れは、技術の問題ではありません。
“補給のタイミング”の問題なのです。
試合後の30分間は「回復のゴールデンタイム」
試合を終えたばかりの選手は、疲れを抱えながらも、まだ身体が“吸収モード”に入ったままです。
この30分の扱い方で、翌日のコンディションが驚くほど変わります。
ガイドラインでは、
炭水化物(リフューエル)+たんぱく質(リペア)+水分・電解質(リハイドレート)
この3つの「3R」を提案しています。
例えば、
・おにぎり+牛乳
・フルーツ+ヨーグルト
・パン+チーズ+スポドリ
どれも特別なものはいりません。
“すぐ食べられること”が、ジュニアには何より大切です。
試合後の過ごし方は、その日の失敗を引きずるか、明日につなげるかを決める静かな分岐点。
回復食は、その分岐点をいい方向に導きます。
試合のための食事は、習慣がつくる戦略
試合前の3時間、試合前の30分、そして試合中、試合後。
それぞれに“役割の違う食事”があります。
難しく考える必要はなく、
「不足する前に入れる」
「消化にやさしいものを選ぶ」
「試合後30分の回復を欠かさない」
この3つができれば、ジュニアの試合は確実に安定します。
次回は、より実践的なテーマとして、「熱中症対策・遠征中の食事・サプリとの付き合い方」をガイドラインの内容からわかりやすく紹介します。