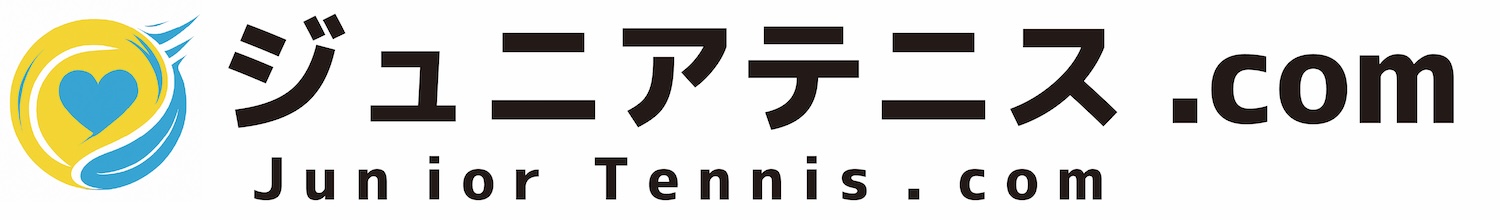“やりたい”という気持ちは、子どもが見つけた小さな宝物。
ある日、テレビで見た錦織圭選手や大坂なおみ選手に憧れて、「ぼくも(私も)テニスやりたい!」と笑顔で言う子ども。
突然の発言に、未経験者の親はあたふた、あたふた。。。
テニスって、何から始めればいいの?
どんな用具が必要だっけ?
どこのテニスクラブがいいの?
ルール、むずっ!?
頭から「?」が限りなく飛び出る、そんな経験をしたことを覚えています。
ネットで調べても出てこないし、周りに知っている人いない。。。
その時に「テニスって、閉ざされたスポーツなんだ」という印象を持った思い出があります。
なので今回、子どもが「テニスをやりたい!」と言ったときに、私のようにあたふたしないように、誰もがスタートを切れるテニスのあれこれを伝えたいと思います。
足りない部分は追記して、良いものにしていきますので、末永く、よろしくお願いいたします。
“やりたい”気持ちを受けとめることから始まる
子どもの「やりたい!」という言葉には、まだ形にならない夢や好奇心が詰まっています。
この時に親がかける最初の言葉が、のちのモチベーションを左右します。
たとえば、「本気でやるなら応援するよ」よりも、「いいね!テニスって、楽しそうだね」と、まず共感から始めるのがおすすめです。
“やる気の火”は、最初は小さなマッチの火のようなもの。
吹けば消えてしまうけれど、優しく風を送れば、少しずつ大きくなります。
テニスの魅力は「自分で考えるスポーツ」
テニスは、ボールを打つ力だけではなく、「どう打つか」「どこに打つか」を考えるスポーツです。
つまり、自分で判断して行動する力を育ててくれる競技。
また、練習相手・コーチ・試合相手と常に関わり合うため、礼儀や感謝の心も自然と身につきます。
海外では“テニスは、人間力を育てる代表的な競技”とも言われています。
(ITF, 2024/Player Development Report)
子育てという観点でも、とても有効ななスポーツなのです。
なぜテニスは“人を育てるスポーツ”なのか
1. 自己判断力・意思決定力を養う
テニスでは、ラケットを握ってボールを打つ「動き」だけでなく、「どこに打つか」「いつ打つか」「相手の次の動きを予測するか」といった判断が必要です。
10週間の意思決定訓練を行った若年テニス選手を対象とした研究では、意思決定能力の向上が技術的パフォーマンスの改善につながったという結果が報告されています。
(Effects of Decision Training on Decision Making and Performance in Young Tennis Players/Gonzalez 他, 2014)
若年テニス選手を対象とした別の研究では、「自己制御(self-regulation)」「人間関係的支援(interpersonal support)」「自尊感情(self-esteem)」が高いほど、試合中の不安が少なく、成長(thriving)と相関があるというデータもあります。(Interpersonal Support, Self‑regulation, and Self‑esteem Effects on Anxiety and Thriving: Evidence from Junior Tennis Players/Wang 他, 2025)
これらは「技術だけでなく、判断力・メンタル・自己マネジメント力」も育てられるという、テニスの大きな魅力と言えます。
2. 認知・実行機能・運動能力の発達
“体を動かす”だけでなく、状況を判断し、適切な反応をする必要があるテニスは、運動能力だけでなく認知面でも育成効果があります。
10〜12歳のテニス選手を対象とした研究では、1年間のモーターコーディネーション(運動の調整能力)に関して顕著な発達が見られたと報告されています。
(One‑year developmental changes in motor coordination and … among 10–12‑year‑old tennis players/Waldziński 他, 2024)
テニス経験と“実行機能”(切り替え・注意・抑制など)との関連を調べた研究では、長期的なテニストレーニングを受けている子どもたちは、こうした認知機能のスコアが高い傾向があるという報告もあります。
(Association between tennis training experience and executive functions in youth players/Xu 他, 2022)
つまり、テニスは「体も頭も動かすスポーツ」であり、学びや成長の場として非常に有効です。
3. 継続・参画・人生への影響
“スポーツ参加”がその後の学び・健康・社会性に影響するという大規模研究のなかで、テニスを行っている若者が他スポーツ・非スポーツと比べて、教育面・健康面・社会的関係でより良い結果を示したという報告もあります。
特に、若年期において「スポーツを通じて得た自信」「人との関わり」「チャレンジする姿勢」は、その後の人生にも良い影響を及ぼすと考えられています。
テニスを“楽しんで続ける”ことで、再参加意向・長期参画意欲が高まるという研究もあります。
(Re‑participation intention in individuals playing tennis for recreational purposes/Karakullukcu 他, 2025)
「一度だけやるスポーツ」ではなく、「続けるスポーツ」としての価値をテニスは持っているので、ジュニア期の体験が長期的な人間育成につながる可能性があります。
「始める年齢」に遅すぎることはない
「もう小学生だし、遅いかな?」と心配する親御さんも多いですが、テニスは年齢より継続と環境が大切です。
4歳から始める子もいれば、10歳で初めてラケットを持つ子もいます。
世界で活躍する選手の中にも、他のスポーツを経験してからテニスに転向した例は多くあります。
ジュニア育成の国際基準では、「多様な運動経験」が推奨されています
(ITF, 2022/Junior Pathway Guidelines)。
走る・跳ぶ・投げる──まずは体を動かすこと全体を楽しむことが、テニス上達の土台になるのです。
最初の1カ月で意識したい3つのこと
1️⃣ “上手くなる”より、“続ける”を目標に
最初の1カ月は、上達より「楽しく通う」ことを目指しましょう。
1回1回の練習が“嫌にならない”ことが、一番の成功です。
2️⃣ 親の期待を押しつけない
「もっと頑張って!」と言いたくなる気持ちを、少しだけ我慢して見守る。
その“待つ力”が、子どもの自主性を伸ばします。
3️⃣ 家でも話題にしてあげる
「今日、ラケットの持ち方覚えたんだね!」など、練習後の会話でテニスを日常に溶け込ませてあげましょう。
子どもは、“親が楽しそうに聞いてくれる”ことが最高の励みになります。
まとめ
テニスを始めるとき、特別な知識や準備よりも大切なのは、
「その気持ちを大切に受け止める親の姿勢」です。
最初の一歩を焦らず、笑顔で。
その瞬間から、子どもだけでなく親子の新しい学びの時間が始まります。
引用元
- ITF (2022). Junior Pathway Guidelines.
- ITF (2024). Player Development Report.