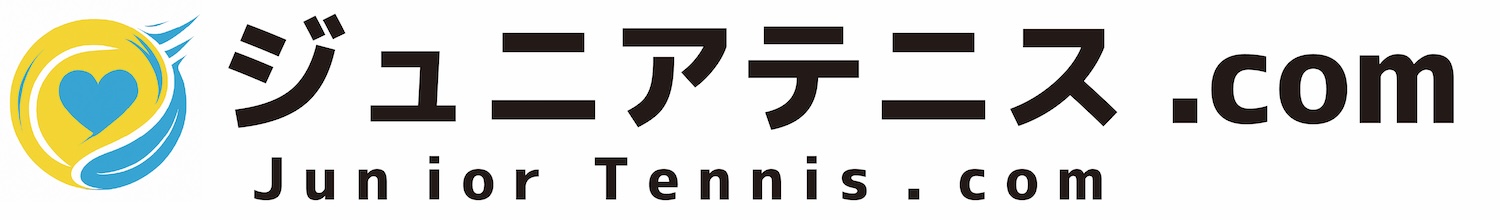「正しい判定」より、「誠実な判断」を。
ジュニアテニスでは、ほとんどの試合がセルフジャッジ(自己判定)で行われます。
つまり、審判はいません。
自分で「イン」か「アウト」かを判断し、自分で相手に伝える。
それは単なるルールではなく、テニスというスポーツが育てたい“心の力”なのです。
セルフジャッジとは?
セルフジャッジとは、試合中に選手自身がライン際のボールを判断し、「アウト」「イン」を宣言する仕組みです。
国際テニス連盟(ITF)のジュニア規定でも、
“セルフジャッジはジュニア育成の基本であり、選手に誠実さと責任感を教える教育的システムである。”
(引用元:ITF, 2023/Junior Fair Play Guidelines)
つまりセルフジャッジは、「正確な目を持つこと」よりも、“自分で決めて責任を持つこと”を学ぶための制度なのです。
基本ルールを知っておこう
セルフジャッジには、いくつかの基本ルールがあります。
難しく見えますが、覚えるのはたったこれだけ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 自分のコートに入ったボールは自分が判断する | 相手のボールを「イン」「アウト」と判定するのは自分。相手コートのボールは相手が判断します。 |
| 2. 迷ったときは“イン”にする | 少しでも迷ったら「イン」。自分に有利に取らないことがフェアプレーの基本です。 |
| 3. 声に出して宣言する | 「アウト!」「イン!」と、相手に聞こえるように伝えます。 |
| 4. 相手を尊重する | 相手の判定に不満があっても、感情的にならず「確認してもいい?」と冷静に伝える。 |
| 5. トラブルのときは主催者・レフェリーへ | コーチや親がコートに入るのはNG。判断はすべて審判員・大会スタッフに任せます。 |
ポイント
“正しく判定すること”より、“誠実に判定しようとする姿勢”が何より大切。
セルフジャッジで育つ3つの力
セルフジャッジは、ただのルールではなく、子どもの成長を支える仕組みです。
① 責任感
自分の言葉で「アウト」と言うことは、“自分の判断に責任を持つ”ということ。
勝っても負けても、「自分で決めた」経験が次の自信になります。
② 誠実さ(スポーツマンシップ)
間違っても、「ごめんね、今の近かったね」と言えること。
それは勝敗以上に価値のある“人としての成長”です。
③ 冷静さ・対話力
判定の違いが起きたときも、「確認していい?」と落ち着いて伝える練習になります。
この“言葉の選び方”が、将来のコミュニケーション力にもつながります。
親ができるサポートは「信じて見守る」
セルフジャッジの場面で、親が一番やってはいけないのは介入することです。
試合中に「今のはアウトだよ!」と口を出すのは、ルール違反であるだけでなく、子どもの“判断する力”を奪ってしまいます。
■親の役割は“見守ること”
子どもが悩んでいるときも、まずは最後まで任せる。
試合後に「どう感じた?」「どんな判断が難しかった?」と対話する。
「きみの判断を信じているよ」と伝える。
この経験の積み重ねが、人としての自立を育てます。
トラブルがあったときの考え方
もし、相手の判定に納得できない場面があっても、その試合全体を“悪い思い出”にする必要はありません。
「あの子ズルい!」ではなく、「自分はどうしたかった?」と問い直すことで、子どもは“自分軸で考える力”を身につけていきます。
試合は勝ち負けの場であると同時に、「信頼」や「誠実さ」を学ぶ教室でもあります。
まとめ
セルフジャッジとは、審判のいない世界で“自分を審判にする”こと。
それは、勝つこと以上に価値のある経験です。
親ができる最高のサポートは、「判断を任せ、信じること」。
その信頼が、コートの上で子どもを一番強くします。
引用元
- ITF (2023). Junior Fair Play Guidelines.
- ITF (2024). Ethical Behavior in Junior Tennis.